久しぶりにカミュの「異邦人」を再読しました。
その感想文です!
まずはネタバレなしで「異邦人」のあらすじをザックリと
「異邦人」は、1942年に発表された小説で、フランスの作家アルベール・カミュの代表作です。
あらすじをネタバレなしで要約すると、こんな感じです。
主人公ムルソーは母親の葬儀でも涙を流さず、翌日には女性とデートし、娯楽映画を見て笑い転げる。数日後、友人のトラブルに巻き込まれる形で殺人を犯してしまう。裁判では母親の死を悲しまないことと殺人が結びつけられ、冷酷なサイコパスのような人間だと捉えられてしまう。
あらすじだけ読むと、「あまり面白くなさそう…」と感じるかもしれません。
ですが、主人公ムルソーの独特の思想、何でもなさそうな前半部分の日常が後半の物語展開のカギとなっていく構成のうまさなど、ガッツリ読みごたえがあり、やはり名作だなと感じます。
「異邦人」は読みにくい?
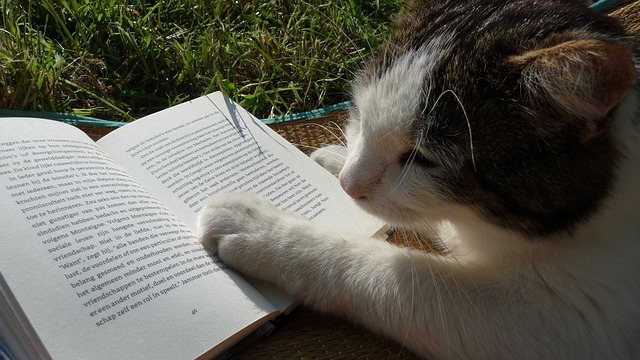
「異邦人」は、店頭で文庫本を手に取ってみると、厚みはなく、結構短い物語です。

本を読むのが遅い私でも、2時間半くらいで読み終わりました。
それほど長い物語ではありませんが、名作外国文学特有の「読みにくさ」がないとは言いきれないかな…というところはあります。
たとえばこれは、物語の終わりの方の文章なのですが、
このとき、夜のはずれで、サイレンが鳴った。それは、今や私とは永遠に無関係になった一つの世界への出発を、告げていた。
新潮文庫「異邦人」より引用
…この部分、何度読んでも、「出発」する主体がわからない…。
主体が「私」だったら、「永遠に無関係になった世界へ」出発するのはおかしいですよね。
もしかしたら翻訳前の原語で読めれば、すぐわかるのかもしれないですが。
こういった感じで、日本語ではすんなり頭に入ってこない文がいくつかはあるため、翻訳小説をあまり読まない方にとっては、少々の読みづらさはあると思います。
タイトル「異邦人」が意味することは?
さて、タイトルの「異邦人」は主人公のムルソーのことを指すというのは、おそらく間違いないでしょう。
ムルソーは、恋人未満の女友達マリイに「変わっている」と言われます。
母親の死に涙を流さず、淡々と葬儀に臨み、翌日には女友達マリイと喜劇映画を見て、初めて関係を持つ…。
ムルソーは死んだ母親の正確な年齢を覚えておらず、母親の死に顔も見ようとしません。
そんなムルソーに対し、人々は「母親さえも愛せない冷血な非人間」という印象を抱きます。
ムルソーは、人間らしい心を持たない=普通の感覚を持った人間が作る社会の一員ではない=異邦人…というわけです。
ムルソーにとっての愛とは?

しかしムルソー自身は、彼なりの感覚で母親を愛しています。
もちろん、私は深くママンを愛していたが、しかし、それは何ものも意味していない。
新潮文庫「異邦人」より引用
ムルソーは母親に愛情はありますが、それはそれだけのこと。
「母親を大事に愛する息子は素晴らしい」みたいな価値観には転換しないのでしょう。
自分の素の感情に意味付けをしないという点では、ムルソーの母親への愛は、本物とさえ言えるかもしれません。
しかし、このようなムルソー流の愛は、世間一般の愛とはあまりにかけ離れています。
家族愛、親子愛、男女間の愛…愛という言葉は、無条件によいものとして捉えられることが多いです。「愛情の深い人間はすばらしい」とでも言うように。
また愛というものは、愛情表現という形で、相手にわかるように伝えるべきだと考える人も多いでしょう。
外部の人々から見ると、母親への愛情表現を見せないムルソーは、母親に対する愛情がまったくないように見えます。
しかし「そう見える」からといって、決して知ることのできない他者の心を決めつけるのは危険なことです。

これは、SNS時代を生きる現代の我々にも警鐘となりますね。
ムルソーの生き方と、わかりやすい物語を求める世界の対立

人間は素の感情に意味づけしがちなものですし、感情だけでなく、起こった出来事、歴史、世界なども、意味や解釈をつけて物語として捉えようとする傾向があります。
その理由は…というと、どんなものも物語化した方がわかりやすいから。

歴史を例にあげると、シンプルな年表を淡々と追うより、ストーリー仕立てになった漫画で読んだ方が頭に入りやすいですよね。
物語の最後に、ムルソーはキリスト教司祭からの抱擁を拒否します。
ムルソーが拒否した理由は、宗教とは世界を解釈したものだからではないか…?と、私は考えています。
ムルソーの口ぐせや、心の中でよく発されるセリフは「どうでもいいこと」「どちらでもいいこと」です。
ムルソーにとって、あらゆるものには意味はない。
私の未来の底から、まだやって来ない年月を通じて、一つの暗い息吹が私の方へ立ち上ってくる。その暗い息吹がその道すじにおいて、私の生きる日々ほどには現実的とはいえない年月のうちに、私に差し出されるすべてのものを、等しなみにするのだ。他人の死、母の愛―そんなものが何だろう。いわゆる神、ひとびとの選びとる生活、ひとびとの選ぶ宿命―そんなものに何の意味があろう。
新潮文庫「異邦人」より引用
「一つの暗い息吹」とは、やはり「死」でしょうね。
ぶっちゃけて言うと、「どうせ死んだら無になるのだから、生きている間の出来事に意味なんかない」といったところでしょう。
ほとんどニヒリストに見える彼が持っているものは、「あらゆるものに意味はない。だから解釈はせずにそのまま受け止める」という人生哲学なのではないでしょうか。
ムルソーのニヒリズムに近い人生哲学は、わかりやすいものを求める世界とは、当然ながら対立します。
この男に見出されるような心の空洞が、社会をものみこみかねない一つの深淵となる
新潮文庫「異邦人」より引用
…これは、検事がムルソーへ死刑求刑する理由を述べているセリフの一部です。
ムルソーが裁判の聴衆たちに憎まれ、世界からの排除(=死刑)を求められたのは、「ムルソーがあまりにわかりにくく世界の物語内におさまらないから」という側面があるのではないかと思います。
ちょっと話が飛躍しますが、私は、ニヒリズムは必ずしもネガティブな思想ではないと考えています。
自分自身の生や、世界に、意味がないということは、むしろ人生を自由に生きていくことにつながるのではないかと。
物語の最後にムルソーが幸福感を抱くのは、ムルソーの人生哲学は、彼自身にとっては悲観的なものではないからなのでしょう。
まとめ
カミュ「異邦人」の感想でした。
カミュの「異邦人」は、小説そのものも、意味づけや解釈を拒否しているような面もあり、主人公の性格や話の流れに一貫性を感じないところもあります。
ですが、現実の人間や世界とはそれほど秩序立った存在ではない…「異邦人」が表現するのは、そういったことなのかな…と思います。
「異邦人」の主人公は被害者への罪の意識はほとんどなく、その部分はどうしても不快感を持ってしまいます。
主人公が一言でも罪の意識に触れていれば、もう少し小説の印象も変わるのでしょうが、「異邦人」である主人公が読者の期待にこたえないのが、この小説の本領なのかもしれません。
というか、「異邦人」は小説というより、哲学書として読むほうがいいのかも…なんてことも思いました。





